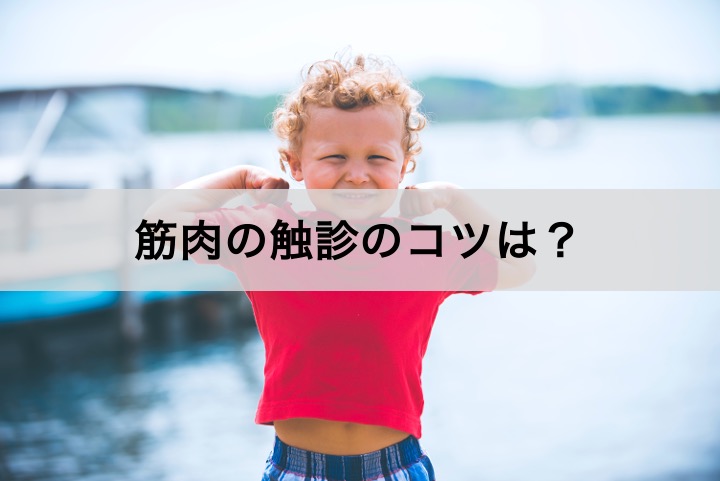 Books
Books 筋肉の触診のコツは?
筋肉の触診のコツは?こんにちは、ひろかずです。セラピストにとって、筋肉をしっかりと触診するスキルは基本中の基本です。筋肉の触診のコツはあるのでしょうか?いろいろとノウハウはあるかと思いますが、徹底して正常を理解することこれが本質かと思います...
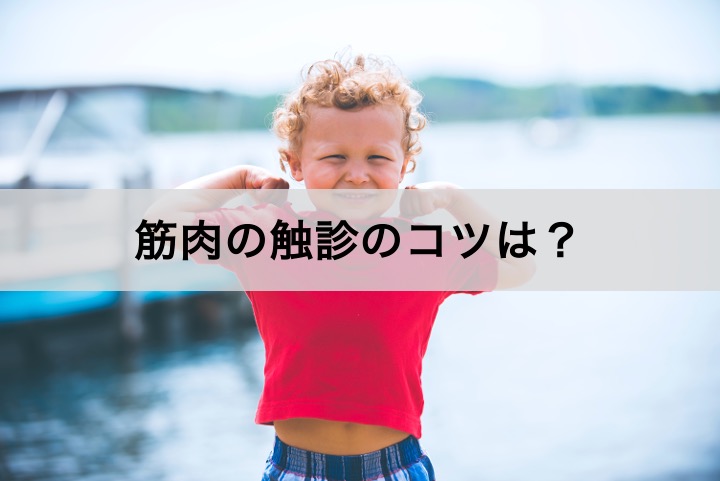 Books
Books 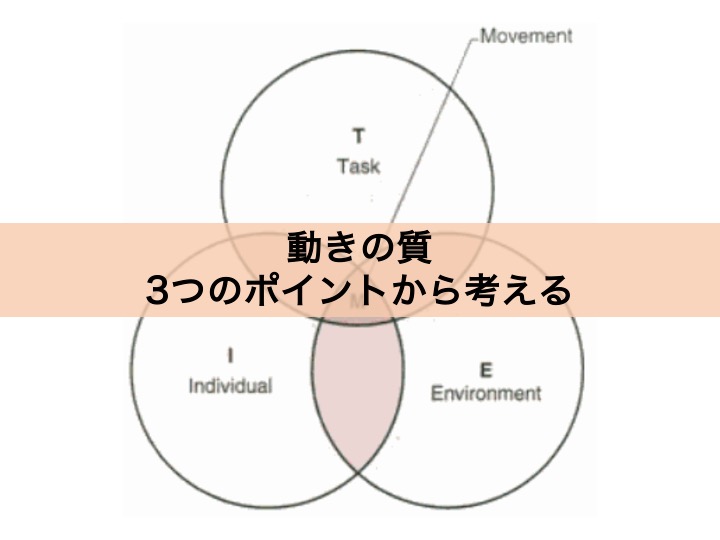 Clinical
Clinical 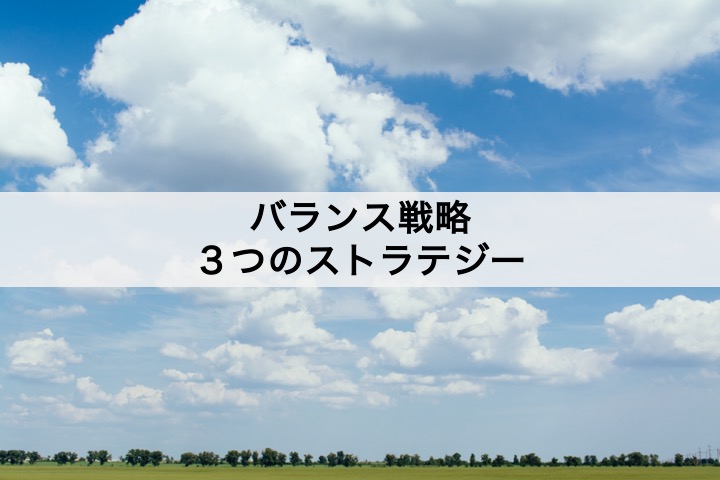 Clinical
Clinical  Clinical
Clinical  Clinical
Clinical  Clinical
Clinical 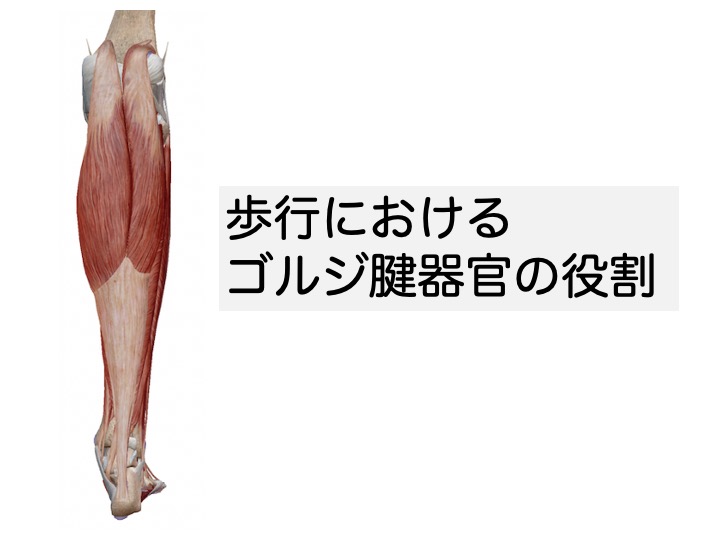 Clinical
Clinical  Clinical
Clinical  Clinical
Clinical  Clinical
Clinical